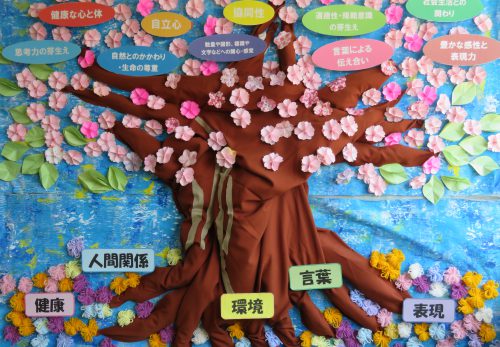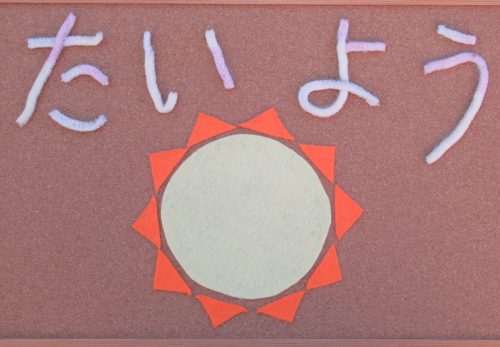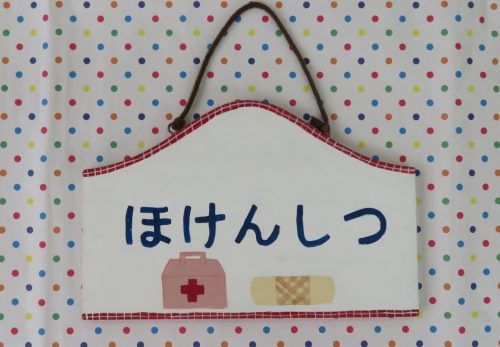9月からずっと続いている虫の罠大作戦。
今週は生き物に詳しい志知先生(環境教育推進員)、伊藤先生を講師にお招きして、一緒に畑で虫の罠を仕掛けたり、捕まえた虫を観察したりしました。

事前に帰りの会で、どんなことをお尋ねしたいか子どもたちと話題にした時には、「罠をどこに仕掛けるといいか」や「生き物がどんな餌なら食べるか」を知りたいと話していました。

その時にはあまり意見が出なかった子も、当日志知先生や伊藤先生と畑に出向くと、先生方の手を引いたり、自分が見てもらいたい罠の場所まで案内したりして、「この虫は何っていう虫なの?」「ここに罠を仕掛けてみたけれど、どうかなあ?」「どんな場所にトカゲは集まるの?」と次々質問していました。予定時間があっという間に過ぎてしまうほど、熱中して罠を仕掛け、生き物を追いかけていました。
志知先生に「トカゲやカナヘビは昼間の時間に、こういったコンクリートのところに出てきて、ひなたぼっこをするよ。」と教えてもらい、これまでに作っていた「2階建ての生き物マンション」を増築して、たくさんの子どもたちが罠を仕掛けました。(セメントブロックが高く積まれていて、若干危険なようにも思いますが、子どもたちなりの工夫と作戦です。お近くを通られる際は、ご注意ください。)

大騒ぎで、一部の子にしか紹介できなかったのですが、実はこの日、新たにハサミムシが罠にかかりました!!

畑のカブやダイコンの生長をいつも楽しみに、確認しているのですが、なんとカブの葉が穴だらけになっていました。「え?!食べられているよ、何かに。」「なんで?」と目を凝らし、葉を1枚1枚見てみると、小さな青虫がついていました。志知先生によると、シジミチョウの幼虫だそうです。確かに最近、シカクマメの植えてあるあたりをよくシジミチョウが飛んでいます。「あれか〜!」と成虫の姿と幼虫の姿が結びつき、体験と知識が結びついて、どんどんわくわくが膨らみました。そんな話をしていると、白くなった幼虫が土の上を動いていました。よく見ると、死んでしまった幼虫を無数のアリたちが運んでいるところでした。「生」と「死」を目の当たりにし、「餌になるのかな・・・」と見つめていました。


遊戯室でも、映像や実物を使って、いろいろな罠の仕掛けがあること、餌にもさまざまな種類があることなどを教えていただきました。餌に用いるものとして、「魚肉ソーセージ」「さなぎ粉」「ミミズ」などの実物を見せてもらったり、匂いを嗅いだりしました。

「くっさーい!」「なんか魚みたいな匂いがする・・」と言いながら、何度も匂いを嗅いでいました。
その後、志知先生の育てていらっしゃる生き物たちを見たり、触ったりさせてもらいました。



志知先生が飼育されていたニジイロクワガタを園へいただきました。
珍しい生き物がいると、子どもも大人も、ついつい飼育ケースを覗きこんで見てしまいますね(笑)
生き物について、興味・関心が膨らみ、ますます生き物好きが加速しているように感じています。

翌登園日に早速教えてもらった方法で罠を作りました。
「これどういう順番で穴に通すの?」と見本としていただいたものと、にらめっこ。
これまでよりも少し複雑な作りの罠でしたが、自分の力で作り上げることができました。


餌は、さなぎ粉、生きたミミズ、煮干しなどバリエーション豊かです。(これも志知先生からいただきました。)生きたミミズを入れたら、早速ミミズが逃げ出しそうになっていて、「餌なんだから、ダメ!ちゃんと罠の中にいて!!」と大慌てでした。

またまた、おもしろくなってきた罠づくり。もうしばらく楽しみたいと思います。