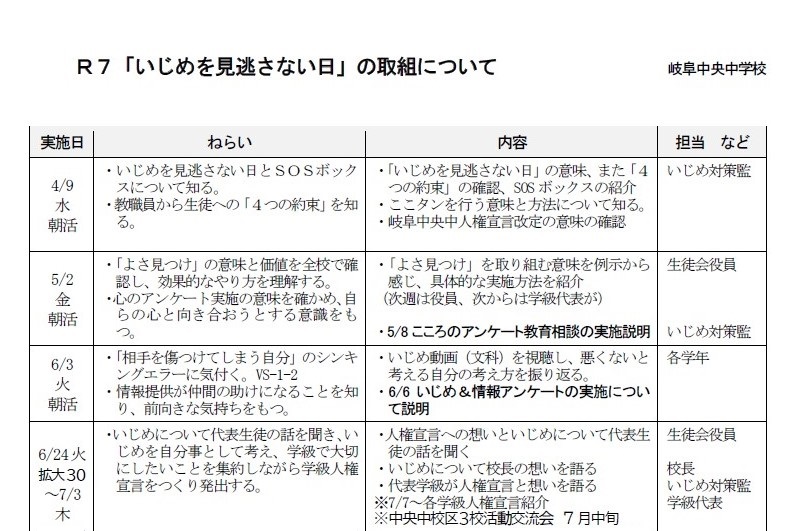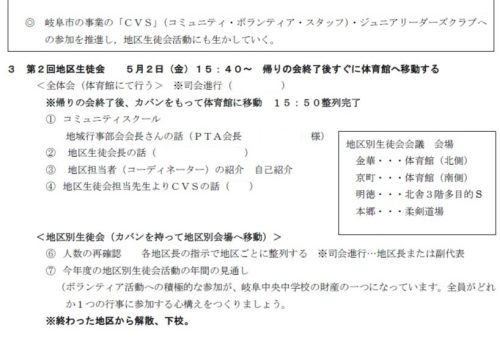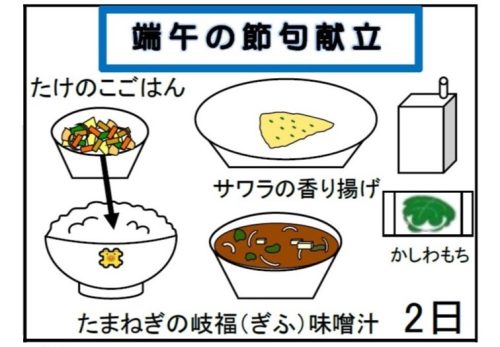5月2日、「いじめを見逃さない日」として、生徒会長より「よさ見つけ」について話がありました。
《生徒会長の話》
みなさん、おはようございます。
今日は、「いじめを見逃さない日」ということで、
生徒会役員を代表して、「よさ見つけ」の意味ややり方についての話をしたいと思います。
まず、「よさ見つけ」とは、どんな活動なのでしょうか。
わたしは、「相手のよい行動から、どんな気持ちで行動したのか、そこから考える相手のよさとは何か」を見つける活動だと思います。
ここで大切なことは、「よい行動」で終わることがないようにするということです。
例えば、だれかが「黙々と掃除をしていた」というよい行動があった時、
「黙々と掃除をした」という事実、行動で終わらずに、
そこから「学校をきれいにしたいという思いで掃除をしていたのではないか」という相手の気持ちや思い、願いを見つけ、
「自分の仕事をしっかりとやりきることができるというよさがある」のように、
相手の本当のよさを見つけることが大切です。
これは、「いじめのない学校」を目指すために、
お互いのよさを認め合い、尊重し合うための一つの手段として行うものです。
ただ、昨年度の姿を見ていると、
途中から、「よさ見つけ」をすることが目的になってしまっていることも少なくありませんでした。
みなさんには、この「よさ見つけ」を
「いじめのない学校」を目指すための手段であることをしっかりと認識してほしいです。
目的と手段をはっきりと分けましょう。
このような「よさ見つけ」の意味を理解することで、
「よさ見つけ」に対する意識が変わっていくのではないかと思います。
これはわたしが考える「よさ見つけ」です。
みなさんは、それぞれで「よさ見つけ」の意味や効果について考えをもてるとよいですね。
*写真は各教室で放送を通じて生徒会長の話を聞いている様子です。
 岐阜市立岐阜中央中学校
岐阜市立岐阜中央中学校